一般貨物自動車運送事業許可の申請代行専門!東京都の行政書士事務所
一般貨物自動車運送事業の許可申請専門!東京都の行政書士事務所
あさひ行政書士・社会保険労務士事務所
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-4-22-503
042-476-8198
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
|---|
各種手続のお申込みは、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、
ご送信願います。
一般貨物自動車運送事業
経営許可申請代行手数料
トラック・霊柩(5両以上)
200,000円(消費税別)
霊柩(車両5両未満)
170,000円(消費税別)
<全国対応・代行手数料全国一律>
<営業所1ヶ所のみの場合の代行手数料です>
費用の詳細はこちらをクリック
※最適・最少金額の
所要資金計画を作成!

選ばれるのには理由があります
はじめまして、行政書士の小久保と申します。
毎年、数多くの一般貨物自動車運送事業に関連する許認可申請・届出手続などのご依頼を受けておりますが、その半数以上が既存のお客様からのご紹介によるものです。
当事務所を選んでいただける大きな理由は、金額だけではなく、申請までの処理が迅速であり、申請内容が確実なので許可取得までにかかる時間が早いことが挙げられます。
安かろう悪かろうではご紹介はいただけませんから、当事務所の実績が評価されていると自負しております。
以下、具体的にご説明させていただきます。
行政書士・社会保険労務士
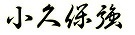
代行費用を200,000円に設定できる理由とは
お客様からは『どうしてそんなに代行費用が安いのですか?』といったご質問をよく受けます。
理由は「運送事業に特化した行政書士事務所」だからです。
行政書士報酬は自由報酬制ですから、各行政書士が自由に決めることができます。
私たち行政書士が提供する商品(サービス)は、「物」ではなく「知識とノウハウ」です。
その「知識とノウハウ」の提供にかかる原価は、主に労力(単価×時間)です。
この原価に事務所運営に必要な間接費用、利益などを上乗せして代行費用を決めていますので、労力が大きい程、代行費用は高めになります。
行政書士は運送事業の許認可申請手続に限らず、その他数多くの事業に関する許認可申請手続の代理・代行業務を法的に認められていますが、一人の行政書士が全ての事業の許認可申請手続に精通することは、到底不可能です。
運送事業に関連する許認可申請手続を繰り返し経験することで、運送事業の許認可に関する知識とノウハウが蓄積されていきますので、当然ながら、運送事業の許可申請手続に精通している行政書士ほど、1件あたりの申請手続に要する労力コストを少なくできます。
当事務所には、運送事業の許認可申請手続に特化してきたことによる知識とノウハウが蓄積されておりますので、申請業務に要する労力コストは格段に少ないので、代行費用を高く設定する必要がないわけです。
一方で、運送業専門と謳いながら、代行費用50万円以上といった驚くような金額のところもあります(サラリーマンの1ヶ月の平均給与額をはるかに超える金額ですね)。
1件でどれだけの利益を皆さんから得ようとしているのか、何故そんなにもコストが掛かるのか聞きたくもなります。
皆さんは、同じメーカーの同一車種の新車を50万円で販売しているディーラーと20万円で販売しているディーラーのどちらを信用してご購入されますか。
代行費用については、その事務所の費用と利益のバランスについての考え方もあるのでしょうから否定はしませんが、「運送業許可申請の代行費用は○万円~が相場です。」と謳っているようなところは、やめておいた方がいいでしょう。
運送業許認可で大切なことは、相場ではなく、その許認可に精通している行政書士であるか否かです。
当事務所で許可取得をされたお客様が、一様に口を揃えておっしゃることは「50万円、60万円も出費しなくて良かった。」です。
当事務所の代行費用は、業務に精通している当事務所にとっての適正料金です。
許可を取得しただけでは運輸開始はできないことにご注意ください!
勘違いをされている事業主の方が多いのですが、新規許可を取得しただけでは、営業ナンバーは取得できませんし、もちろん運輸開始もできません。
下表の「代行費用とサポートの範囲の比較」の運輸開始までの手続の流れをご覧ください。
許可取得後に営業ナンバーへ変更登録をするためには、その前に「運行・整備管理者選任届の提出」、「運輸開始前の確認報告書の提出」、「事業用自動車等連絡書の提出・交付」の3つの手続が必要となります。
許可後の費用を別料金としている行政書士事務所もありますので、代行費用を比較される際はご注意ください。
代行費用とサポートの範囲の比較(金額は消費税別)
当事務所 200,000円 | O事務所 300,000円 | B事務所 500,000円 | |
| 1.許可申請書類の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.許可申請書類の提出 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.審査期間中の補正対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ー許可ー | ー | ー | ー |
| 4.運行・整備管理者選任届の提出 | 〇 | × | 〇 |
| 5.運輸開始前の確認報告書の提出 | 〇 | × | 〇 |
| 6.事業用自動車等連絡書の提出・取得 | 〇 | × | 〇 |
| ー営業ナンバー登録ー | ー | ー | ー |
| ー運輸開始ー | ー | ー | ー |
| 7.運賃・料金設定届の提出 | 〇 | × | 〇 |
| 8.運輸開始届の提出 | 〇 | × | 〇 |
*〇は代行費用に含まれるもの、×は別料金となるもの
目次に戻る
運送事業の許認可に精通している行政書士ほど早く確実
一般貨物自動車運送事業の許可申請手続は、専門知識を必要としますので、見様見真似で申請しても審査を通りません。
申請事業者ごとの状況に応じて、どのような書類を用意し、申請書類にどのような内容を記載すべきかは全く異なります。
特に申請書類の「事業計画」や「資金計画」の作成には、運送事業関連法の知識以外に、労働基準法、最低賃金法、労働・社会保険関連法などの知識も必要となります。
申請事業主ご自身で申請する場合や運送事業の許認可申請に不慣れな行政書士の場合、申請までの間に右往左往して時間を無駄に費やすことになります。
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請は、審査の標準処理期間(平均審査期間)だけで3ヶ月~5ヶ月を要します。あくまで標準処理期間であり、絶対期間ではありません。時期や地方運輸局の業務量などにより変動しますし、申請書類に不備・不足などがあれば、審査期間はさらに延びますので、審査の標準処理期間(平均審査期間)は最低必要処理期間と考えておいた方がよいでしょう。
そのため、短期間で許可を取得するためには、いかに申請までの期間を短縮し、かつ審査において重大な補正事項が生じない正確な申請書類を作成することが重要となります。
最悪なのは、単なる見様見真似で申請書類を作成、提出してしまうことです。補正ができないような不備が発覚すれば、申請を取り下げなくてはならなくなります(実際に年に数件、再申請のご相談があります)。
行政書士は数多くの業種に関する許認可申請手続を代理・代行することが認められている士業ですが、その全ての業種に精通することは不可能であり、一人の行政書士が精通できる業種は、せいぜい数種類に限られます。
必ずしも『行政書士=運送事業許可の専門家』というわけではないことにご注意ください。
当事務所は、一般貨物自動車運送事業の許認可申請・届出手続に特化し、精通することで、お客様ごとのあらゆる状況に応じて、どのような書類を用意し、どのような内容の申請をすればよいのかを正確に判断し、迅速で確実な申請手続を行っております。
一日でも早く、かつ確実な許可取得をご希望されるなら、「事業主ご自身による申請」や「何でも屋の行政書士による申請」より「運送事業の申請業務に専門特化した行政書士」にご依頼されることをお勧めいたします。
目次に戻る
最少金額の所要資金計画を作成できます
一般貨物自動車運送事業の許可申請においては、所要資金計画(事業開始に要する資金及び調達方法)の書類を作成したうえで、その合計金額以上の自己資金を有していることを、金融機関発行の残高証明書で証明する必要があります。
例えば、所要資金計画の算出金額が1,500万円であれば、少なくとも1,500万円以上の残高証明書の提出が必要となるわけです。
許可申請書類の中で一番に難しいのが、この所要資金計画(事業開始に要する資金及び調達方法)の作成であり、作成ルールと関係法令に抵触しない範囲で、かつ最少金額にすることが重要になってきます。
誰がこの所要資金計画を作成するかによって、算出合計金額に大きな差が生じます。
仮に作成ルールと関係法令に精通していない行政書士が作成すれば、作成ルールや関係法令に抵触して審査が通らないか、所要資金が膨らみ過ぎて自己資金を準備できない、といった事態も起こることでしょう。
当事務所なら、作成ルールや関係法令に抵触するような資金計画は作成しませんし、最少の自己資金の準備で済む資金計画を作成できます。
所要資金計画は、前述の誰が作成するのかといったこと以外にも、法人申請・個人申請の別、人員計画、車両の大きさ、車両の使用権原(自己所有・購入・割賦・リースの別、価格・割賦金・リース料)、営業所や車庫の使用権原(自己所有・賃貸の別、賃料)、その他様々な要因により数百万円以上の差異が生じます。
因みに当事務所では、トラック運送の法人申請で一千数百万円、霊きゅう運送の法人申請で300万円~500万円前後の資金計画になるケースが多いです。
当事務所では所要資金にご不安な事業者の方向けに、「所要資金シミュレーションサービス(有料:税別20,000円)」も行っておりますのでご利用ください。なお、お支払いいただいた当該シミュレーション費用は、運送事業の許可申請をお申込みの際に申請代行費用から控除いたします。
資金計画の作成についての詳細はこちらをクリック
所要資金シミュレーションサービス(有料)についての詳細はこちらをクリック
目次に戻る
役員法令試験
一般貨物自動車運送事業に専従予定の常勤役員のうち1名(個人事業者の場合は事業主自身)が、許可申請後に実施される役員法令試験を受験し、合格しなければ許可を取得できません。
どんなに完ぺきな許可申請書類を作成したとしても、当該法令試験に合格できなければ、申請書類の内部審査に進むことなく、許可申請は却下若しくは取り下げることになります。
当該法令試験に合格するためには過去問題の学習が不可欠です。
早くから過去問題を繰り返し学習し、出題傾向を掴んで本番に臨んだ方ほど、1回目の法令試験で合格しています。法令試験は2回受験チャンスがありますが、当然、1回目で合格した方が許可までの期間が短くなります。
許可申請することを決めたら、すぐにでも過去問題の学習に着手することをお勧めいたします。
※地方運輸局ごとの過去問題は、各地方運輸局のホームページ上に公開されています。
役員法令試験対策についての詳細はこちらをクリック
目次に戻る
運送事業の認可・変更届なども格安でご提供
許可取得後も、営業所・車庫の変更、車両の変更、毎年提出しなければならない事業報告書や事業実績報告書など、さまざまな手続が必要となる場面があります。
これらの面倒な手続きからも解放されるように、当事務所に一般貨物自動車運送事業の経営許可申請手続等をご依頼いただいた事業主の方については、費用負担の少ない格安料金で代行しています。
【営業所新設認可申請の代行手数料】50,000円(税別)
【増減車変更届の代行手数料】10,000円(税別)~
目次に戻る
各種助成金 のご提案・手続代行
当事務所は社会保険労務士事務所を併設しています。
運送事業のように多くの労働者を必要としながらも、労働者の採用・定着が難しいとされる業種については受給可能性の高い助成金が数多くあります。
当事務所に許可申請をご依頼いただいた事業所様には、助成金受給可能性の無料診断、申請代行(有料)を行っています。
目次に戻る
運送業のための顧問契約・経理代行・社会保険手続
運送業界では、社会保険への加入指導、その他労務管理面の指導が強化されています。
当事務所は社会保険労務士事務所を併設していますので、社会保険に関するご相談もお受けできますし、格安で手続代行しています。
また、社会保険加入により、いっそう複雑になる毎月の給与計算も代行しております。
さらに、毎年、運輸局に提出が必要となる「事業概況報告書」、「事業実績報告書」の作成に支障が生じないように、毎月の経理から決算までを格安料金で代行しています。
【顧問契約】10,00円(税別)/月~
【経理代行】9,500円(税別)/月~
【給与計算】6,000円(税別)/5名まで~
目次に戻る
許可申請手続代行手数料
一般貨物自動車運送事業許可申請の代行料金
| 営業所の所在地の管轄運輸局 | 代行手数料(消費税別) |
全国の運輸局一律 | (トラック運送・申請車両5両以上の霊柩運送) 200,000円 (申請車両5両未満の霊柩運送事業) 170,000円
*申請営業所が1ヶ所のみの場合の代行手数料です。 |
*特積み許可は除きます(特積み許可申請代行手数料は別途、ご相談ください)。
*前金制となります。着金確認後の業務開始となりますのでご了承ください。
*許可取得後には、法定費用(登録免許税)12万円の納付が必要です。
*許可申請書類の作成・提出から許可取得、許可取得後の「運輸開始前の確認報告」、「運行・整備管理者選任届」、「運輸開始届」、「運賃料金設定届」までの手続を全て行います。
「許可取得後の手続は別料金です。」といった不親切な料金設定ではございません。
ただし、許可取得後の各手続につきましては、当事務所が手続ごとに指定する期日までに必要書類をご準備いただくことが前提条件です。当該指定期日までに必要書類をご準備いただけない場合は有料となります。
*お客様が行う作業は、「当事務所から指定させていただく書類のご準備」と「許可後に車両を陸運局に持ち込んで営業ナンバーに付け替える」ことだけです。
*別途、交通費等をご請求することもございません。
*許可申請中(運輸局審査中)に申請内容をご変更される場合(車両、営業所、自動車車庫などの変更)は、別途申請手続が必要となりますので、その際は追加料金が発生いたします。
【ご留意事項】
当事務所の責めに帰すべき理由によって、許可を取得できなかった場合は、直ちにお支払いいただいた代行手数料を返金いたします。
業務着手後のお客様都合によるキャンセルや、お客様のヒアリングシートへの虚偽のご記入や虚偽のご回答、期日までに必要書類をご用意いただけなかった場合など、お客様の責任により許可を取得できなかった場合はご返金いたしかねますのでご留意願います。
会社設立手続の代行料金
一般貨物自動車運送事業の許可申請前に株式会社を設立したい方
| 本店所在地 | 代行手数料(消費税別) |
| 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 | 40,000円 |
| 上記以外の関東地方 | 50,000円 |
| 関東以外 | 60,000円 |
*前金制となります。着金確認後の業務開始となりますのでご了承ください。
*別途、会社設立に係る法定費用(定款認証手数料、登録免許税等)約20.2万円が必要です。法定費用は、どなたが手続を行う場合でも必ず納付が必要となります。
*会社設立時に発起人が出資する出資金(資本金)は1円以上とされています(現実に資本金1円とする会社は少ないですが…)。
出資金(資本金)は国等に納付するものではなく、発起人(代表)の預金口座に振込み(入金)することにより証明します。
*登記申請書類は司法書士が提出します(若しくはご自身でご提出いただきます)。
目次に戻る
お客様の声
- お願いして良かったのは、一番は許可申請の代行手数料の安さ、二番目は社会保険や記帳代行などのオプションの手続も格安なところ(一部抜粋)。
(M運輸株式会社様/東京都) - 運送事業は、許可取得後も運送車両の変更手続きや毎年提出の営業報告書、事業実績報告書の作成が大変なので、会社の近くで安い行政書士事務所を中心に探していました。
手続きに慣れている行政書士さんだったの安心してお任せできました(一部抜粋)。
(株式会社S様/東京都) - 会社設立から運送事業の許可申請までをお願いしました。おかげさまで開業前のあいさつ回りの営業に専念できました。運送事業は許可取得後も運送車両の変更や毎年提出の営業報告書などもあって大変のなので、現在は顧問契約と毎月の経理代行をお願いしています(一部抜粋)。
(T株式会社様/東京都) - 一般貨物運送事業の許可取得を検討していました。正直、どこに頼んだらいいのかわからなかったので、取引先の同業者に紹介でお願いすることにしました。
申請までの手際が良く、別の行政書士さんよりずっと手続きに詳しかったので、行政書士さんにもいろいろいるんだな、というのが正直な感想ですね。
それから、助成金を500万円以上取得できたのもすごく助かりました(一部抜粋)。
(有限会社O建設様/東京都) - 中古車販売事業者ですが、これまで、都度、臨時運行許可で運送するか、運送事業者に運送委託していましたが、大幅に販売車両数が増えてきたのでコストもかさんできました。
同業者からの紹介で回送運行許可申請をお願いしました。1ヶ月ちょっとでディーラーナンバーを取得できました。
業務量が増えてきた時期で社員増員と福利厚生面の整備を検討していることをご相談したところ、助成金のご提案をしていただき、そのまま申請代行と社会保険手続もご依頼しました。
ホームページに書いてあったとおり、安くて確実に手続きをしてもらえる点がとても信頼できます(一部抜粋)。
(株式会社O様/埼玉県) - 許可申請をお願いした理由は、やっぱり費用が安かった点です。顧問契約と経理代行までをお願いしたのは、一般貨物自動車運送業は変更手続も多いし、毎年の報告書の提出手続きもあるので大変だからです。
手続のスケジュール管理、会社の経理までしてもらえるので、安心して業務に専念できています。(一部抜粋)。
(株式会社R様/東京都) - 霊きゅう運送の許可申請をお願いしました。詳しくなかった必要人員、営業所、駐車場、車両などの要件について、しっかりとアドバイスいただいたので、とても助かりました。
法令試験や巡回指導についての疑問点にも対応していただき、本当にありがとうございました。
(株式会社S様/埼玉県)
目次に戻る
よくあるご質問
ここではよくある一般的なご質問をご紹介します。
許可申請についての個別の疑問につきましては、「許可のポイント」のページをご覧ください。
茨城県に事務所がありますが、格安プランを申し込めますか?
はい、お申込みいただけます。
格安代行プランは、設置する営業所の管轄運輸局ごとに設定しております。
他の行政書士事務所で許可を取得しましたが、認可申請や変更届出手続も依頼できますか?
はい、お申込みいただけます。
許可取得後の認可申請や各種届出手続やオプション手続きなどもご利用いただけます。
申し込みたいときは、どうしたらいいですか?
お申込フォームから必要事項をご入力のうえ、ご送信ください。
お申込みページのフォームに必要事項をご入力のうえ、ご送信ください。
当事務所から許可申請ヒアリングシートを送信いたします。
ご返信いただくヒアリングシートの内容によって、ご用意いただく書類やデータなどの詳細をご連絡いたします。
料金はいつ支払うのですか?
お申し込み後、業務着手前までに指定口座にお振込みいただきます。
ご入金確認後の業務着手とさせていただいております。なにとぞ、ご了承ください。
許可を取得できなかった場合は、料金を返金してもらえますか?
はい。当事務所に責任がある場合は、ただちに返金いたします。
当事務所の責めに帰すべき理由によって、許可を取得できなかった場合は、ただちに返金いたします。
当事務所は事前診断により、許可の基準を満たせるか否かを十分にチェックしてから正式にご依頼をお受けいたしますので、これまで当事務所の責任で許可が取得できなかったケースはございません。
なお、お客様のヒアリングシートへの虚偽のご記入や虚偽のご回答、期日までに必要書類をご用意いただけなかった場合、役員法令試験に2回とも不合格の場合など、お客様の責任による場合はご返金できません。
商品・サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
目次に戻る
オプションサービスのご案内
運送業許可ブログ
2026年1月15日
2026年1月13日
2025年12月26日
2025年12月24日
302025年12月22日




